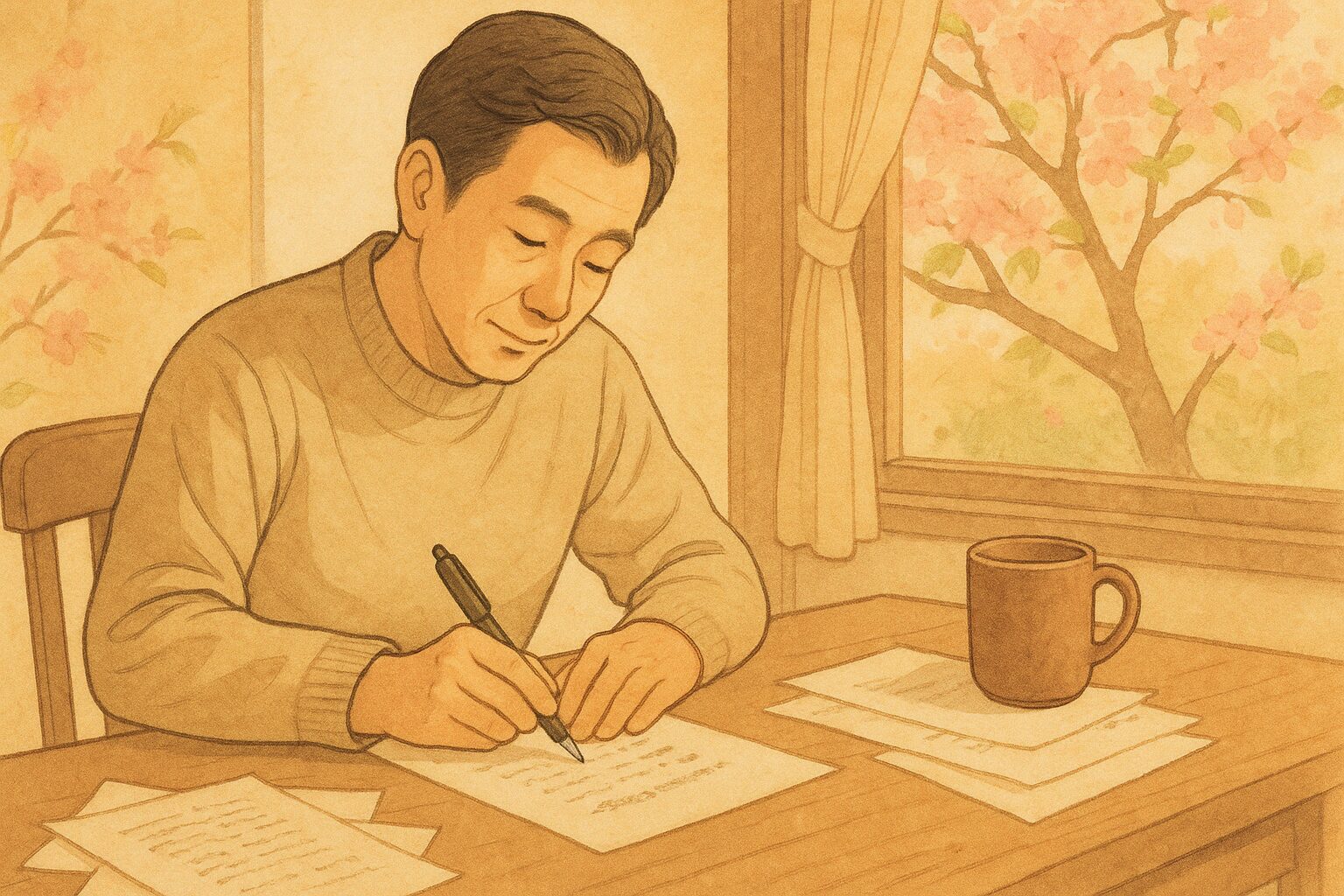「編集後記」は、記事やニュースレター、社内報、広報誌などのコンテンツの末尾に添えられる短い文章ですが、その影響力は決して小さくありません。読者との心の距離を縮め、筆者の“人となり”を感じさせることで、情報発信に温かみや共感を生み出します。
とはいえ、いざ「編集後記を書いてください」と言われると、手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。何を書けばいいのか、どのような言葉遣いが適切なのか、そして読者の心に響くにはどんな工夫が必要なのか。こうした疑問は、すべての書き手が一度は抱える悩みです。
この記事では、「編集後記 例文」を中心に、書き方の基本から具体的なテンプレート、さらには媒体別・季節別のネタ例、共感を呼ぶテクニック、AI活用法まで網羅的に解説していきます。特に実用性を重視し、すぐに使える例文を多数ご紹介するので、「明日の発行に間に合わせたい」といった場面でも安心です。
文章が苦手でも大丈夫。読者に自然と伝わる“あなたらしさ”を引き出すヒントを、ここでたっぷりお届けします。
編集後記とは?目的と役割をわかりやすく解説
編集後記の基本定義とその歴史的背景
編集後記とは、新聞や雑誌、社内報、広報誌などの末尾に掲載される短い文章であり、発行者や編集者の「あとがき」のような役割を果たします。記事内容とは少し距離を置いた、筆者の個人的な感想や裏話、制作裏話などが綴られることが多く、読者にとっては一種の「余白」として楽しみにされる存在です。
この文化の起源は、印刷媒体が主流だった昭和の新聞にさかのぼります。当時の新聞では、記者が取材の裏側や報道に対する思いを綴った「後記」欄があり、それが編集後記のルーツとされています。社内報や広報誌が広く発行されるようになった高度経済成長期には、情報発信の一部として定着しました。
たとえば、ある食品メーカーの広報誌では、季節ごとの食材紹介の後に、編集者が「最近自宅で味噌汁に使っている野菜」について語ることで、内容に温かみを加えていました。こうした“人間味のある語り”が、読者の心に自然と残るのです。
したがって、編集後記は単なる余白ではなく、記事全体のトーンを和らげ、筆者の想いを届ける重要な要素であるといえます。
読者との距離を縮める編集後記の効果
編集後記には、読者との心理的な距離を縮める効果があります。なぜなら、形式的な情報ではなく、筆者個人の「声」が感じられるからです。情報があふれる現代において、信頼できる情報源は「人」であるという考え方が定着しつつあります。そのような中で、編集後記は“顔の見える発信”の役割を果たします。
たとえば、PTA広報誌で「今月は娘の遠足にボランティアとして参加しました」といった一文を添えることで、読者である保護者との共感が生まれます。単なる活動報告に留まらず、身近な日常の共有を通じて、親近感を得ることができるのです。
しかも、編集後記は正式な「報告」ではないため、多少のくだけた表現や、感情を込めた言葉も許容されます。その自由さが、読者の感情に寄り添いやすく、温かい印象を与えるのです。
このように、編集後記は読者との“心の通路”として機能し、広報活動の中でも極めて重要な意味を持ちます。
社内報・広報誌・メルマガなど媒体ごとの違い
編集後記は、掲載される媒体によって求められる内容やトーンが異なります。たとえば、社内報の場合は企業文化や職場内の雰囲気を反映した文章が好まれます。一方で広報誌では、企業の対外的イメージやブランド性を損なわないよう、丁寧かつフォーマルな表現が求められます。
メルマガではさらに自由度が高まり、発信者の個性やユーモアを活かした軽快な文章が歓迎される傾向があります。これはメールというメディアの特性上、読み手が「個人」として受け取ることが多く、形式ばった文よりもカジュアルな文体の方が読者に響くためです。
たとえば、社内報であれば「今月は●●部の新メンバーが加入しました。意外にも釣りが趣味だそうで…」といった軽いトピックを入れると、自然に職場内の雰囲気が伝わります。
媒体ごとの編集後記のスタイルを意識することは、読者との適切な関係構築にもつながります。そのため、発行媒体の性格をよく理解した上で、トーンや語彙の選定を行う必要があります。
次に、編集後記の構成そのものについて深掘りしていきます。
まずはここから!編集後記の基本構成と書き方
起承転結で自然な流れを作るコツ
編集後記を書く上で大切なのは、読みやすく自然な流れを意識することです。そのために最も効果的なのが、古典的でありながら普遍的な「起承転結」の構成です。この構成を使えば、短い文章でも伝えたいことが整理され、読者にとっても内容がすっと頭に入ってきます。
まず「起」では、話題の導入として日常のちょっとした出来事や時事ネタを取り上げます。たとえば「今朝、通勤途中に咲いている桜を見て春を感じました」といった一文は、季節感を伝えると同時に親しみやすい導入になります。
次に「承」で、起の内容に関する少し深い思いや背景を展開します。先ほどの桜の例なら、「毎年この時期に桜を見ると、新入社員時代を思い出します」と続けることで、個人的な回想や感情が読者に伝わります。
「転」では、一見関係なさそうな話題や驚きを交えて展開を転換します。たとえば「今年は例年より開花が早かったせいか、社内の花見企画が少し慌ただしくなりました」というように、業務と関連させると、社内報などには特に適しています。
そして「結」では、全体をまとめ、読者に向けたメッセージや感謝の気持ちで締めます。「皆様もどうか体調に気をつけて、春を楽しんでください」と結べば、優しさのある終わり方になります。
このように、新聞やメールなどの媒体においても、構成を意識するだけで編集後記に説得力が生まれ、読者の印象にも残りやすくなります。
失敗しない語尾・表現の工夫
編集後記では語尾の使い方や表現の工夫が、全体の印象を大きく左右します。文章の終わり方ひとつで、読者に与える余韻がまるで異なるため、特に気を配るべきポイントです。
たとえば、堅苦しい社内報の場合でも「〜でした」「〜と思います」といった語尾を使うことで、やや柔らかさを加えることができます。逆に、すべての文末が「〜します」「〜です」と続くと、単調で無機質な印象になることもあるので、あえて一文だけ「〜なんてこともありました」とくだけた表現を挿入するのも効果的です。
また、PTAの広報誌などでは、子育てや家庭にまつわるエピソードが多いため、「〜でしたね」「〜でしょうか」といった読者に寄り添う語尾が適しています。たとえば「朝の忙しさは年々増している気がします。皆さんもそう感じることはありませんか?」といった問いかけで締めると、親近感が増します。
とはいえ、表現が砕けすぎると媒体の品格を損なう可能性もあるため、編集後記の文体は「発行媒体の性格に応じたバランス感覚」が必要です。加えて、広報としての立場を意識しつつ、時には“委員”のような親しみやすい視点を取り入れると、文章に深みが出ます。
このように、語尾や表現を意識するだけでも編集後記の質は大きく向上します。
「です・ます」か「である」か?文体の選び方
編集後記における文体の選択は、「です・ます調」と「である調」のどちらがふさわしいかを見極めることが重要です。基本的には、読者との関係性や媒体の性格を考慮して選びます。
たとえば、メルマガやPTAの広報誌のような親しみを重視する媒体では、「です・ます調」が自然で柔らかい印象を与えるため、多くの編集者に選ばれています。この文体は、感情表現や会話調の文とも相性が良く、読者に話しかけるようなトーンを作り出せます。
一方で、社内報やビジネス寄りの媒体では「である調」を選ぶこともあります。この文体は論理的かつ信頼感のある印象を与えるため、フォーマルな雰囲気を必要とする場面に適しています。ただし、冷たくなりがちなので、語彙選びや文の長さで調整する必要があります。
例えば、「今月の社内報は、技術部の活動に焦点を当てた内容である。現場の声を多く盛り込み、リアルな姿を届けた。」というように、情報の信頼性を重視する文体が好まれる場合に向いています。
とはいうものの、どちらの文体にも長所と短所があるため、状況に応じて混在させる“ミックスタイプ”も近年では増えています。実際、広報誌の編集部では「本文はである調、後記はです・ます調」と使い分けることで、柔軟に読者層にアプローチしています。
それでは、次に実際の例文を見ながら編集後記の書き方をさらに具体的に学んでいきましょう。
例文で学ぶ!使える編集後記テンプレート5選
社内報にぴったりのフォーマルな例文
社内報に掲載する編集後記では、社内の一体感を促すと同時に、業務とのつながりや成果を簡潔に振り返ることが重要です。フォーマルでありながら、柔らかさもある表現が求められます。
以下は実際に使える例文です。
—
「今号では、営業部の新プロジェクトを特集しました。プロジェクトに関わったメンバーへのインタビューを通じて、現場での努力や工夫が多く見えてきました。取材を終えた後、改めて“現場にこそ力がある”と感じた次第です。
季節の変わり目で体調を崩しやすい時期ですが、皆様が元気に業務に取り組めることを願っております。」
—
このように、文中に社内の「活動」や実際の「発行」内容を触れることで、読者である社員が自分ごととして受け取りやすくなります。
次に、もう少し柔らかさと親しみを加えた、PTA向けの例を見てみましょう。
PTA広報誌に使える親しみやすい例文
PTA広報誌では、読み手の大半が保護者であることから、家庭的な話題や育児に関する内容が共感を得やすくなります。形式ばらず、日常の延長線上にあるような文章が好まれます。
以下は一例です。
—
「最近、小学2年生の息子が『ママは委員って何してるの?』と聞いてきました。説明しながら、子どもたちのために大人も“見えないところで活動している”ことを改めて感じました。
運動会の準備や校外学習の付き添いなど、忙しいながらも楽しいPTA活動が続いています。皆さまも無理なく、ご自身のペースで関わっていただければと思います。」
—
このように、子どもとの会話や家庭での出来事を織り交ぜると、読者に寄り添う表現となり、広報としての信頼感も増します。
それでは、次はメルマガ向けの少し砕けた文体の例を見ていきましょう。
メルマガに合う軽快で砕けた例文
メルマガは読者との距離が近く、ビジネスやサービスの情報提供に加え、発信者の個性やユーモアが求められる場面が多くなります。したがって、少しくだけた文体や日常の「あるある」ネタが効果的です。
以下は例文です。
—
「こんにちは、編集担当の山田です。
先日、久しぶりに手帳を買い替えました。最近はスマホで予定管理してたのですが、どうしても“手書き派”に戻りたくなる瞬間があるんですよね。
ちなみに、今月のメルマガでは新サービスのご案内に加えて、お得なキャンペーンも掲載しています。チェックはお早めに。」
—
このように、私的なエピソードから始めることで、メールを読んでいる“個人”に向けた親しみやすい印象を与えることができます。メルマガにおける編集後記は、本文とは違うトーンでの発信が読者の記憶に残りやすいため、差別化のポイントにもなります。
続いては、季節感を活かした編集後記の工夫について解説していきます。
季節感を活かす!月別の編集後記ネタ例
春:新生活・花粉症・桜などをテーマに
春は新生活が始まる季節であり、編集後記に使える話題が豊富です。入学・入社といったライフイベントや、桜や花粉症といった季節感あふれるテーマは、多くの読者が共感しやすい要素です。
たとえば、広報誌に掲載する編集後記であれば次のような一文が考えられます。
—
「新年度が始まり、通勤電車の中でも真新しいスーツを着た新入社員の姿を多く見かけます。自分の入社当時を思い出し、なんとも言えない気持ちになりました。今年も社内報を通して、皆様の頑張りを少しでも伝えていけたらと思います。」
—
また、PTA広報誌では花粉症の話題も身近です。
「春は桜とともに花粉も舞う季節。朝の登校見守り活動の際、マスク越しにくしゃみが止まらない日がありました。季節の変化を感じながら、子どもたちの成長を見守るこの時間もまた、大切なものだと改めて感じています。」
このように、春の編集後記では“季節の実感”を軸に、自然な語りで読者との心の距離を縮めることが可能です。
夏:暑さ・イベント・夏休みネタを盛り込む
夏は気温の上昇とともに、行事も盛りだくさんの時期です。地域イベントや子どもの夏休み、業務の繁忙など、編集後記に取り上げる話題に事欠きません。
たとえば、新聞の地域版やメールマガジンであれば、次のような表現が活用できます。
—
「猛暑が続く中、週末は地域の盆踊りに参加してきました。子どもたちの浴衣姿と笑い声が、夏の夜にぴったりの風景でした。
取材に協力いただいた皆様、暑い中ありがとうございました。夏休み後半戦も、熱中症に注意しながら乗り切りましょう。」
—
また、社内報であれば業務との関連性を持たせた編集後記も効果的です。
「今月は製品の出荷が例年よりも早まり、物流部門の皆様には特にご尽力いただきました。猛暑の中での作業、本当にお疲れ様です。編集後記ではありますが、この場を借りて感謝を申し上げます。」
このように、季節と“活動”を組み合わせることで、読者の関心を引きやすくなります。
秋冬:行事・年末・感謝を表す言葉選び
秋から冬にかけては、文化祭や運動会、忘年会や年末の総括といった行事が目白押しです。また、1年の締めくくりとして「感謝」の表現が自然と求められる時期でもあります。
たとえば、年末発行の広報誌での編集後記には、次のような文が適しています。
—
「今年もあとわずかとなりました。本誌の発行を通じて、多くの方々の声や笑顔に触れられたことが、私たち編集チームの励みとなりました。来年も引き続き、地域や職場の“今”を伝えていけるよう努めてまいります。どうぞ良いお年をお迎えください。」
—
また、PTA広報誌であれば次のような親しみある締め方も喜ばれます。
「秋のバザーでは、準備にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。季節の変わり目は体調も崩しやすくなりますが、温かいお茶でも飲んで、少しほっとする時間が持てますように。」
このように、秋冬の編集後記では「お礼」「ふり返り」「温もり」のある言葉選びを心がけると、読者に深く届く文章となります。
それでは、続いて「読者の心をつかむ共感を生むテクニック」に入っていきましょう。
読者の心をつかむ「共感」を生むテクニック
感情を引き出すストーリーテリングとは
編集後記において最も読者の印象に残るのは、情報ではなく「感情」です。ストーリーテリングとは、個人の体験や具体的な場面描写を用いて、読者の感情に働きかける文章技法です。これは編集後記でも有効に機能し、読者の共感を引き出す手段となります。
たとえば、あるメルマガでの編集後記が次のような内容だったとします。
—
「先週末、父と2人で釣りに行ってきました。幼い頃によく連れて行ってもらっていた場所で、何年ぶりかの再訪でした。昔話をしながらのんびり糸を垂らす時間は、日常の忙しさを忘れさせてくれました。」
—
このように、明確なストーリー展開があり、読者が情景を思い浮かべやすい記述は、それだけで印象に残りやすくなります。しかも、共起語としての「活動」も盛り込むことで、読者に“人となり”を伝えることができます。
ストーリーテリングは長文である必要はありません。短い中にも心を動かす瞬間があれば、それが共感につながるのです。
具体例と自分の体験談を織り交ぜる
読者にとって“リアル”な文章とは、書き手の体験が具体的に語られているものです。特に、共通体験や“あるある”と感じられる事象は、編集後記で共感を得るための鉄板ネタといえるでしょう。
たとえば、PTA広報誌では次のような例が挙げられます。
—
「運動会でリレーに出場した娘の姿を見ながら、小学生だった自分の姿と重ねてしまいました。あの頃のように全力で走ることはもう難しいですが、今は陰ながら応援する側になった自分を誇らしく思います。」
—
このような“自分語り”は、一歩間違えると自己満足に見える可能性もありますが、読者と体験を共有できるテーマであれば、むしろ親しみを生みます。新聞のコラムや社内報でも、自分の中の小さな発見を丁寧に書くことが、読者の心を動かす鍵となります。
だからこそ、編集後記には自分の体験談を臆せずに織り交ぜることが大切なのです。
問いかけや呼びかけで読者を巻き込む
編集後記は一方的に語るだけではなく、読者を巻き込む意識が必要です。そのためには、問いかけや呼びかけを積極的に活用しましょう。
たとえば、
「皆さんは最近、何か“新しいこと”を始めましたか?」
「寒い朝が続きますが、今朝の空気には少しだけ春の匂いが混じっていた気がします。」
こうした問いかけや詩的な描写は、読者の中にイメージを喚起し、自然と文章へ引き込む効果があります。特にメールマガジンでは、こうした軽やかな導入や締め方が高い効果を発揮します。
また、読者の存在を意識した言葉選びは、「メール」を通じて双方向性のある関係を築くきっかけにもなります。
このような工夫を施すことで、編集後記は単なる締めの文章ではなく、読者との絆を育む場として生きてきます。
次に、注意したいNG例と改善法を確認していきましょう。
やってはいけない編集後記のNG例と改善法
感情の押し売り・内輪ネタに注意
編集後記でやってしまいがちな失敗のひとつが、「感情の押し売り」や「内輪ネタ」に頼ってしまうことです。たしかに、自分の気持ちを素直に書くことは大切ですが、読者が置いてけぼりになるような表現では共感は得られません。
たとえば、以下のような文章は避けるべきです。
—
「いや〜、本当に疲れた1ヶ月でした。会議も多かったし、◯◯さんとのやりとりも大変で…。正直、今は何も考えたくない気分です(笑)」
—
このような書き方は、感情が先走りすぎて読者の理解を得られませんし、特定の関係者だけがわかる“内輪話”は、広報の文脈としても不適切です。
改善するなら、次のような工夫が効果的です。
「今月は業務が立て込み、特に調整の多い期間でした。そんな中でも、部署間の連携でなんとか乗り越えることができ、チームの強さを実感しました。」
このように、感情を客観化し、「誰にとっても共通のテーマ」に落とし込むことで、読者にも受け入れられやすくなります。
抽象的すぎる内容は伝わらない
もう一つのNGポイントは、「抽象的すぎる」内容に終始してしまうことです。「がんばります」「感謝しています」「日々学びです」など、気持ちは伝わりますが、それだけでは読者の印象に残りません。
たとえば、次のような表現では弱く感じられます。
「今月も色々なことがありましたが、多くの学びがありました。」
こうした内容は具体性がなく、どんな出来事だったのか、どんな気づきがあったのかが伝わらないため、読者が読み流してしまいます。
改善例としては、
「今月は新人教育の一環として3回のOJTに同行しました。現場での“なるほど”の瞬間に立ち会うたび、自分も初心に戻る思いがしました。」
このように、「具体的な行動+気づき」の形で構成すると、読者がイメージしやすくなり、文章の深みも増します。
文字数のバランスと改行の工夫
最後に、意外と見落とされがちなのが「文字数」と「改行」のバランスです。編集後記は長すぎると読み飛ばされ、短すぎると味気なく感じられます。一般的には300〜500文字が適切とされますが、媒体によっては600〜800文字でも構いません。
加えて、改行を入れずに文章を詰め込んでしまうと、読者にとっては読むのが苦痛になります。とくにWEB媒体やメールマガジンでは、段落ごとに1行空けるだけでも読みやすさが大きく変わります。
実際、広報誌の担当者の中には「文章の構成よりも改行位置の方が大事」と語る人もいるほどです。読者の読みやすさを第一に考えるなら、視覚的なレイアウトにも気を配るべきです。
次は、忙しい担当者向けに「AIを活用した編集後記の時短術」をご紹介します。
AIも活用可能?編集後記の時短ライティング術
ChatGPTで編集後記をサポートする方法
近年、編集後記の執筆においてもAIの活用が進んでいます。特に、ChatGPTのような生成AIは、時短の強い味方となります。キーワードを入力するだけで、骨組みのある文章案を提示してくれるため、忙しい広報担当者やPTA委員にとっては非常に心強い存在です。
たとえば、「春 新生活 入学 不安」というキーワードを入力するだけで、
—
「新生活が始まり、我が家も長男の中学校入学を迎えました。慣れない制服に少し照れている様子が、頼もしくもあり、ほほえましくもあり…。新しい環境で頑張るすべての皆さんに、心からエールを送りたいと思います。」
—
このように自然な文が生成されます。これをベースにして、自分の体験や気づきを加えれば、オリジナルの編集後記がすぐに完成します。
キーワード入力だけで例文を自動生成
AIの便利な点は、キーワードの組み合わせ次第で何通りもの編集後記案を得られることです。たとえば、メール配信前の数分間に「今月 活動 PTA」と入力すれば、すぐに親しみやすい文面を得ることができます。
また、定型文のベースとしても使えるため、毎月の発行業務のルーティン化にも役立ちます。特に社内報やメルマガでは、「導入文+近況+締めのあいさつ」という基本構成があらかじめ決まっている場合が多いため、AI生成と相性が良いのです。
ただし、そのままコピー&ペーストでは“人間らしさ”が薄れる点には注意が必要です。
人間らしさを加える最終仕上げのコツ
AIが生成した文章を活かすには、最終的な“人間らしさ”の仕上げが不可欠です。具体的には、自分だけの体験談や気持ちを一文加えること、それだけで大きく印象が変わります。
たとえば、AIが提案した文に次のような一文を追加するだけで、共感度が増します。
「実はこの文章を書いている今日、近所の小学校では入学式が行われていました。門の前で記念写真を撮る親子の姿に、胸が温かくなりました。」
このような情景描写は、AIでは出せない“空気感”や“温度感”を生み出します。AIと人間、それぞれの強みを活かすことで、効率と感情のバランスを両立した編集後記が完成します。
次は、編集後記を活かしたSNS・WEBでの活用方法について見ていきましょう。
編集後記が活きる!SNSやWEBとの連携活用法
WEBメディアでのリライトと再利用
編集後記は、紙媒体だけでなくWEBメディアやSNSでも再活用することで、情報発信の幅を広げることができます。特にブログや企業サイトにおいては、編集後記部分を“読み物”として切り出すことで、SEOやファン形成にも貢献します。
たとえば、広報誌で掲載した後記をWEB版にリライトする際、冒頭に「今月の広報担当のひとこと」として掲載し、関連する記事やお知らせへのリンクを付ければ、情報導線としても機能します。
また、新聞記事の「コラム」として再編集することで、読者の“人となり”への関心を引き、継続読者を増やすことにもつながります。WEBでは文字数の制限が比較的緩いため、紙面では語りきれなかった裏話を加えるのも効果的です。
このように、編集後記はWEBメディアとの連携によって、単なる締めの文章から“読者との接点”へと進化させることが可能です。
InstagramやX(旧Twitter)での応用
SNSでは、編集後記の中でも特に“共感”や“人間味”のある部分を切り出して投稿するのが効果的です。たとえばInstagramでは、写真に合う短い文章や一言コメントを編集後記から引用すれば、自然なストーリーとして発信できます。
X(旧Twitter)では、日常の気づきや感謝の言葉など、140字以内で収まるように工夫して編集後記のエッセンスを投稿すれば、多くの反応が得られます。たとえば、
—
「今日の空気は春の匂い。桜の蕾がふくらむのを見るたびに、また1年が始まる気がします。#編集後記 #春の気配」
—
このような投稿は、写真やハッシュタグとの組み合わせで“温度感”を持った情報発信となり、読者の心に残りやすくなります。
QRコードで紙からデジタルへの誘導
紙媒体の広報誌や社内報では、編集後記の最後にQRコードを設け、WEBサイトやSNSへの導線とする工夫が注目されています。これにより、読者が紙から自然にデジタルメディアへ移行でき、情報発信の継続性が生まれます。
たとえば「もっと詳しい話はWEBでご紹介しています」と記載し、QRコードを添えることで、読者の関心をオンラインへと広げることができます。企業や団体の活動がオンライン上でも見える化されることで、ブランドの信頼性向上にもつながります。
PTA広報でも、「当日のイベント写真はPTAサイトで掲載中です」といった導線を編集後記に仕込むことで、紙とWEBの役割を連携させた広報が実現します。
まとめ:編集後記はあなたの“想い”を伝える場
一文一文が読者との架け橋になる
編集後記は、読者との距離を縮め、伝えたい“想い”を柔らかく届けるための特別な場所です。短い文章であっても、一文一文が大切な架け橋となり、媒体の印象を大きく左右します。社内報や広報誌、メルマガ、PTAだよりなど、どの媒体であってもその効果は変わりません。
完璧を目指すより“等身大の言葉”を
完璧な文章でなくても構いません。むしろ、背伸びをせず、自然な自分の言葉で綴ることが、読者の共感を呼びます。たとえば、少しのユーモアや照れを含んだ一文が、読者に安心感や親しみを与えることもあります。
広報活動や発行作業に追われていても、ほんの数分で気持ちを込めた一文を書けるようになると、編集後記はあなた自身の信頼の証になります。
楽しんで書くことが一番のコツ
そして何より、楽しんで書くことが、よい編集後記を生む最大のコツです。自分の体験を共有する、読者の笑顔を想像する、そんな小さな喜びを感じながら言葉を紡ぐことで、文章にも自然と温度が宿ります。
読まれる編集後記とは、書き手の“心”がにじみ出ているものです。だからこそ、今日からあなたも気負わずに、まずは一行から始めてみてください。