「造園業 やめとけ」とネットで検索すると、ネガティブな情報が多く目に入ります。たしかに、造園業は自然と関わるやりがいのある仕事である一方、過酷な現場環境や不安定な収入といった厳しい現実も隠せません。
この記事では、実際に現場で働く人々の声やリアルなデータを元に「やめとけ」と言われる理由を徹底解説します。また、造園業に向いていない人の特徴や、続けるメリット、将来性、具体的なキャリアパスまで詳しく紹介します。これを読むことで、造園業という仕事を選ぶべきか、改めて考えるきっかけになるはずです。
造園業はやめとけと言われる本当の理由とは?
過酷な肉体労働と長時間労働
造園業は見た目以上に体力を必要とする仕事です。たとえば、真夏の炎天下で1日中重たい植木を運ぶ作業や、土を掘り返す作業は、慣れない人にとって大きな負担になります。それに加え、長時間労働が常態化している現場も多く、朝早くから夜遅くまで現場にいることが珍しくありません。
なぜなら、植物の生育状況や気候に左右されるため、決まったスケジュール通りに進まないことが多いからです。ある職人の例では、連日の作業で体重が5kg以上減少したという話もあります。仕事が好きでも、体がついていかないという理由で辞める人は少なくありません。
しかし、しっかりと体調管理をし、休息を取れる環境が整えば続けられる人もいます。だからこそ、体力に自信のない人には「やめとけ」と言われるのです。
低い年収と不安定な収入
造園業の平均年収は300万円前後とされており、他業種と比較すると低い水準です。特に若手や未経験者はさらに収入が低く、生活費を切り詰める必要があります。たとえば、同年代のIT業界に勤める人と比べると、その差は歴然です。
しかも、造園業は季節によって仕事量が大きく変動します。繁忙期には多忙すぎるほど仕事があり、逆に閑散期にはほとんど仕事がなく収入が激減します。そのため、収入が安定しないことにストレスを感じ、転職を考える人も多いです。
それゆえに、安定した生活を望む人にとっては「やめとけ」と言われるのも当然の結果です。
厳しい上下関係と人間関係のストレス
造園業の現場では、上下関係が厳格です。古くからの慣習が色濃く残っており、若手は上司の言うことを絶対に守らなければならない風潮があります。たとえば、新人が先輩に道具の扱いを教わる際、間違った使い方をしただけで厳しく叱責されることがあります。
また、少人数での作業が多いため、人間関係のトラブルが直接的にストレスに繋がりやすいです。特に、チームでの調和を重んじるため、意見を言いにくい環境に悩む人もいます。
そのため、人間関係に悩みやすい性格の人は、造園業の環境に耐えきれず「やめとけ」と言われることが多いのです。
造園業に向いていない人の特徴

体力や忍耐力がない人
造園業では、毎日外での作業が当たり前です。雨の日や寒い日でも現場に出なければならず、体力と忍耐力は必須です。たとえば、真夏の炎天下で植物の手入れをしていると、熱中症のリスクが高まります。そうした環境下でも集中力を保ち続けるには、かなりの体力が必要です。
加えて、突発的な天候変化による作業スケジュールの変更も多いので、柔軟に対応できる精神力も求められます。したがって、体力や忍耐力がない人にとって、造園業は非常に厳しい仕事と言えるでしょう。
自然環境での仕事が苦手な人
造園業は自然と向き合う仕事です。虫に刺されたり、泥で汚れることも日常茶飯事です。たとえば、木の剪定作業中に蜂の巣を発見することもあり、冷静に対応しなければなりません。
このように、自然環境での作業に苦手意識がある人は、精神的な負担を感じる場面が多いです。そのため、自然に囲まれる仕事に夢を抱いて入った人でも、現実に直面して「やめとけ」と感じることが多いです。
細かい作業が嫌いな人
造園業には繊細さが必要です。たとえば、植物の剪定や配置など、細かい技術を求められる作業が多くあります。適当に済ませると植物が枯れたり、景観が崩れたりするリスクがあるため、丁寧さと集中力が必要です。
したがって、細かい作業が苦手で集中力が続かない人には、造園業は向いていない仕事です。これも「やめとけ」と言われる理由の一つです。
造園業のリアルな現場の声

若手職人の挫折体験談
若手職人の中には、理想と現実のギャップに苦しむ人が多くいます。たとえば、ある20代の職人は「自然に囲まれて癒される仕事だと思ったが、実際は重労働と厳しい指導に心が折れた」と話しています。
最初は植物の知識を身につける楽しさを感じていたものの、現場ではスピードや正確さが求められ、のんびりと学ぶ余裕はなかったそうです。こうした現実に直面すると、転職を考える若手が多いのも納得できます。
ベテラン職人が語る厳しさ
一方、ベテラン職人の声を聞くと、造園業の厳しさとやりがいの両方が見えてきます。たとえば、30年以上のキャリアを持つ職人は「体力が続く限り、この仕事を続けたい」と語りますが、同時に「若い頃のように動けず苦労している」とも話しています。
技術の高さが求められるため、常に新しい知識を学ぶ姿勢が必要です。しかし、その技術が評価されると社会的信用を得られる点に魅力を感じる人もいます。
転職者の後悔と本音
造園業から異業種に転職した人の中には「やめてよかった」と話す人もいます。たとえば、30代でオフィスワークに転職した男性は「体力的な負担がなくなり、精神的にも安定した」と語ります。
しかし、自然と触れ合えない寂しさや、造園業でしか得られなかったやりがいを失ったと感じることもあるようです。要するに、どの仕事にも一長一短があるため、自分の価値観と照らし合わせることが重要です。
自然と触れ合える充実感
造園業には、自然と直接触れ合えるという大きな魅力があります。たとえば、毎日さまざまな植物に囲まれて仕事をすることで、季節の移り変わりを感じられるのは大きな特権です。朝露に濡れた葉や、夕方に照らされる花々など、都市のオフィスワークでは味わえない風景があります。
このような環境は、ストレス解消や心の安定に繋がると言われています。実際に、自然の中で作業をすることで「仕事をしているというより自然と一体になっている感覚がある」と語る職人もいます。したがって、自然が好きな人にとっては造園業は特別なやりがいを感じられる仕事なのです。
スキルが一生ものになる
造園業で身につけた技術や知識は、一度習得すれば一生ものになります。たとえば、剪定技術や庭の設計知識は、独立しても活かせるだけでなく、趣味の範囲でも役立ちます。職人の中には、退職後に自宅の庭を自分で整備して楽しむ人もいます。
さらに、経験を重ねるほど、植物の性質を見極める能力が向上し、独自の美的センスを磨くことができます。よって、長く続けることで他業種では得られない唯一無二のスキルが自分の財産になるのです。
地域貢献や社会的評価
造園業は地域の景観や公共施設の整備など、社会貢献度が高い仕事です。たとえば、公園や街路樹の手入れを通じて、地域住民に快適な生活空間を提供しています。
また、地元のイベントや観光地の景観整備に携わることも多く、地域からの信頼や感謝の声を直接受け取ることができます。それゆえに、社会的評価の高い職種として、誇りを持って働けるのが大きな魅力です。
造園業の将来性とキャリアパス
高齢化による人材不足
造園業界では、職人の高齢化が進んでいます。若手の人材が不足しているため、今後は需要がさらに高まると予想されています。たとえば、地方自治体が管理する緑地の整備や維持管理に必要な人材が足りず、技術を持つ若い人材への期待が大きいです。
このように、将来的には経験者が優遇される傾向が強まると考えられるため、今から技術や知識を身につけておくことが有利になります。したがって、若いうちに挑戦する価値がある分野とも言えるでしょう。
独立・起業の可能性
造園業で経験を積んだ後、独立や起業を選ぶ人も少なくありません。たとえば、自分のデザインした庭園や個人宅の庭仕事を請け負うことで、自分のセンスと技術を自由に表現できます。
また、口コミや地域の信頼を得られれば、安定した仕事が入り続ける可能性があります。したがって、自分のライフスタイルに合わせた働き方を実現したい人にとって、魅力的なキャリアパスです。
資格取得でのキャリアアップ
造園業には、造園施工管理技士や樹木医といった資格があります。これらを取得することで、キャリアアップや収入向上が期待できます。たとえば、公共工事の現場責任者になれるなど、より責任あるポジションを任されるようになります。
資格を取ることで、他の職人との差別化もできるため、将来的な独立や転職時にも有利になります。よって、造園業で長期的に活躍したいなら、資格取得は重要な選択肢です。
造園業の収入と生活実態を徹底解説
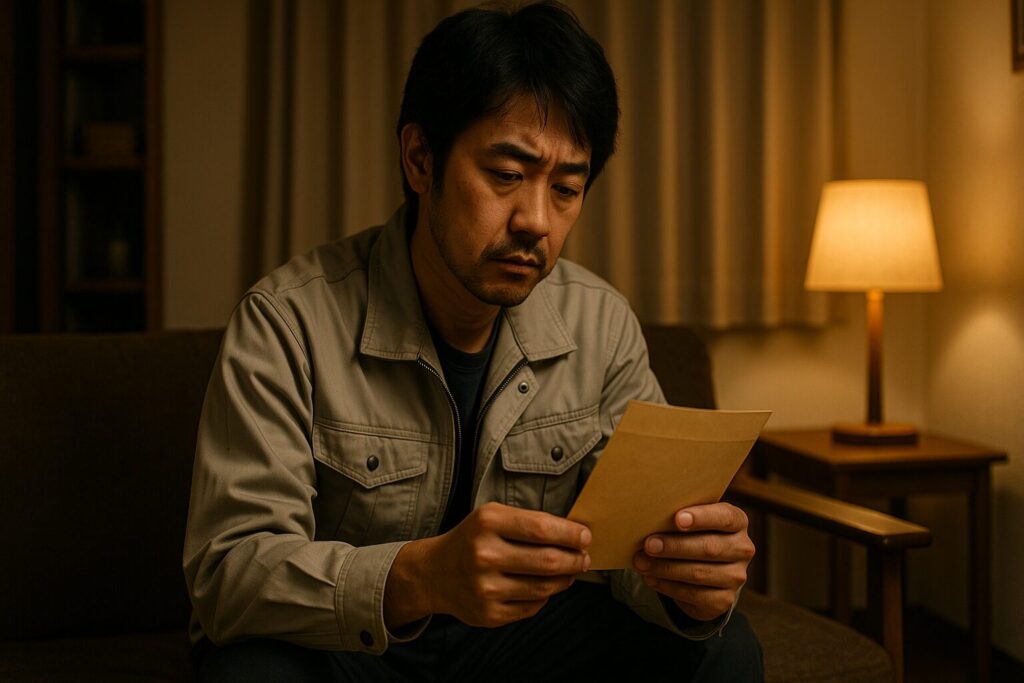
年収と昇給の現実
造園業の年収は経験や会社の規模により異なりますが、一般的に若手の場合は年収250〜300万円程度が多いです。昇給も緩やかで、年齢や経験年数に比例して少しずつ上がる傾向があります。
たとえば、10年以上のキャリアを積んだ職人でも年収500万円に届かないケースも珍しくありません。しかし、技術力を認められたり資格を取得すれば、昇給のチャンスは増えます。とはいえ、安定した昇給を期待するのは難しいため、生活設計を慎重に考える必要があります。
繁忙期と閑散期の収入差
造園業には明確な繁忙期と閑散期があります。春や秋は植栽や剪定などの需要が高まり、仕事量が増えますが、真冬は依頼が少なくなることが一般的です。
そのため、繁忙期には月収が大幅に増える反面、閑散期には収入が激減するリスクがあります。たとえば、繁忙期には残業が多くなる一方で、閑散期にはアルバイトや副業をする職人もいます。収入差に備えて貯蓄や計画的な生活が求められるのです。
副業や独立後の収益性
造園業は独立後の収益性にも差があります。たとえば、個人経営で信頼を築けば、高単価の仕事を獲得できることもあります。一方で、顧客開拓や営業がうまくいかず、収入が不安定になる人もいます。
副業として造園関連の講師や庭園デザインの監修を行う人もいますが、これも技術と知識の積み重ねが前提です。したがって、独立後の収益を最大化するためには、地道な努力と長期的視点が必要です。
造園業に必要なスキルと資格
専門技術と道具の扱い
造園業には多種多様な専門技術が必要です。たとえば、剪定ばさみやチェーンソーなどの道具の正確な扱い、石材や木材の加工技術などがあります。これらは実際の現場で経験を積みながら習得するため、地道な努力が求められます。
正しい使い方を知らないと怪我のリスクがあるため、安全面でも知識は不可欠です。つまり、技術と知識の両方をバランス良く身につけることが大切です。
コミュニケーション能力
造園業では、依頼主とのコミュニケーションが非常に重要です。たとえば、庭のイメージをヒアリングする際に相手の希望を正確に理解し、提案する能力が求められます。
また、現場のチームワークを円滑に進めるためにも、意思疎通は欠かせません。したがって、職人であっても高いコミュニケーション能力が必要とされるのです。
おすすめ資格と取得方法
造園施工管理技士、造園技能士、樹木医などの資格は、業界内での評価を高めるのに有効です。これらは講習や試験を受けて取得しますが、実務経験が必要な場合もあります。
資格取得を通じて、仕事の幅が広がり、転職や独立時にも有利に働きます。よって、将来を見据えたキャリア構築には資格取得が大きな鍵を握っています。
造園業をやめたいと思った時の選択肢
異業種への転職方法
もし造園業をやめたいと感じたら、異業種への転職も選択肢の一つです。たとえば、体力的負担が少ない事務職やIT業界に転職する人もいます。
近年は職業訓練やオンライン講座を利用して新たなスキルを学ぶ方法も増えています。転職先を選ぶ際は、自分の体力や興味、将来の展望を考慮することが大切です。
関連職種へのキャリアチェンジ
造園業の経験を活かせる関連職種にキャリアチェンジする人もいます。たとえば、園芸ショップのアドバイザーやガーデンデザインのプランナーなどがあります。
これらの仕事は、植物や造園で培った知識を活用でき、体力的負担が少ない場合が多いです。したがって、完全に業界を離れなくても新たな道を模索できます。
今の職場で改善する方法
やめる前に、まずは職場環境の改善を検討するのも一つの方法です。たとえば、上司と相談して作業時間や仕事内容の見直しを行う、福利厚生が整った会社に転職するなどです。
改善によって心身の負担が軽減され、続けられる場合もあります。よって、無理に辞める前にできることを試す価値はあります。
造園業で後悔しないためのポイント
事前の情報収集の重要性
造園業に限らず、仕事選びでは事前の情報収集が重要です。たとえば、実際に現場で働いている人の意見を聞いたり、見学に行ったりすることで、ミスマッチを防げます。
また、ネットだけでなく、直接話を聞くことでリアルな現実が見えてきます。これにより、自分に合うかどうかを冷静に判断できるようになります。
自分に合う環境選び
造園業の職場は会社によって雰囲気や働き方が異なります。たとえば、若手を育てる体制が整った職場や、家庭と両立しやすい勤務形態を用意している会社もあります。
自分の性格やライフスタイルに合う環境を選ぶことで、長く続けやすくなります。よって、職場選びも非常に重要です。
メンタルケアと長く続けるコツ
造園業は精神的にも肉体的にも負担が大きい仕事です。たとえば、趣味の時間を持つ、仲間と交流するなど、メンタルケアを意識することで長く続けられる可能性が高まります。
また、定期的に体を休めるスケジュールを組むことも大切です。自分を大切にしながら働くことが、後悔しないための重要なポイントです。
まとめ
造園業は、やりがいや魅力がある一方で、過酷な現場や低い収入、厳しい人間関係といった現実が存在します。体力や自然環境への適応力、技術と知識の習得意欲が求められるため、誰にでも向いている仕事ではありません。
しかしながら、自然と触れ合いながら社会に貢献できる充実感や、一生もののスキルを得られる魅力もあります。重要なのは、自分の価値観やライフスタイルに合うかどうかを見極め、情報収集を徹底することです。そうすれば、後悔のない選択ができるでしょう。



